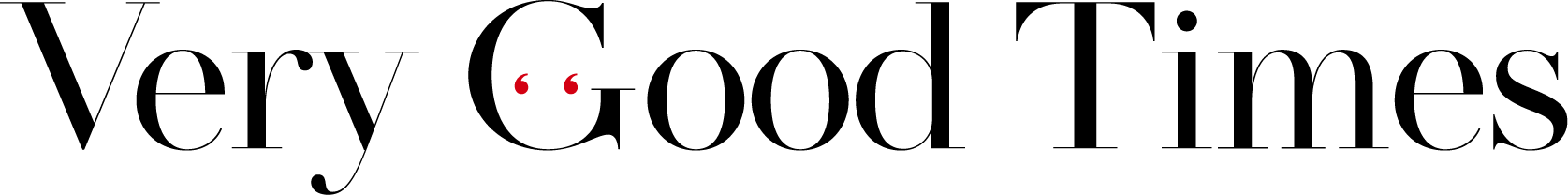美術展らしい美術展にも行ってみよう。と思ったので。
久々に絵画を見に行きます。
デザイナーだけど美術関係素人の私が(いまさらながら)美術に触れよう、というこの企画。最初こそは名だたる画家の作品が集う“美術展”に行ったものの、その後、ガラス工芸のイッタラ展や、美術というより、歴史的価値を感じに国宝展に行ったりと、ちょっと趣旨を踏み外しそうなので、今回は、美術展らしい美術展に行ってきました。
今回訪れたのは上野の国立西洋美術館で2023年3月18日〜6月11日まで行われる『憧憬の地 ブルターニュ』展です。多くの画家たちに愛されたブルターニュ地方を描いた絵画にテーマを絞った、まさに“美術展らしい美術展”です。

ブルターニュってどこ?
「ブルターニュ」。正直、どこにあるのかも、何が有名なのかも知らないけれど、なんとなく名称だけは聞いたことがある、という程度の馴染み。何も知らないよりはと思い、行きの電車の中で、ブルターニュについて調べてみます。フランスの左上の突き出たところ、あとちょっとでイギリス。緯度は北海道より高いけど、西岸海洋性気候のおかげで、夏は30℃ぐらいまで上がるとか。パリやロンドンとは遠く文化的発展も近代までは遅れ気味の様子。反して、仲のよろしくなかったかつてのイギリスとフランスの間とも言える場所に位置するため、政治的には微妙な立ち位置。シードルやガレットが名産品として有名・・・・一緒に行った社会科の教師をやっている友人によれば、日本だと、東北地方みたいなものだと。少し寒くて、開発が進んでいない、田舎感がある地域、ということなのだそうです。
館内でのガイドによれば、そんな田舎の原風景みたいなものへの憧れが芽吹き出した1800年代、「ピクチャレスク・ツアー(絵になる風景を探す田舎への旅)」なるものが流行ったらしく、それにジャストフィットだったのがブルターニュなのだそう。クロード・モネやポール・シニャックがこの地を訪れて描いた作品も。いずれも、当時のパリをはじめとした都会で見られる景色とは異なる風景への新鮮さに突き動かされて描いたことが伝わってくるようでした。
絵と記憶がリンクする感覚
今回の展示で一番心に留まったのはポール・ゴーガンの1枚でした(かつては“ゴーギャン”と呼ばれていたと思うのですが、しぶしぶ、ゴーガンで統一します)。<ボア・ダムールの水車小屋の水浴>という作品。
ゴーガンの代表作といえば、タヒチで描かれたオリエンタルでエキゾチック、楽園感あふれる作品たち。彼はタヒチへ行く前、このブルターニュで創作活動を行っていました。タヒチにもブルターニュにも共通していたのはきっと、文明に覆われていない在りのままの自然と、そこに暮らす人たちの素朴な日常。この<ボア・ダムールの水車小屋の水浴>も、そんな日常の風景を切り取った1枚。夏の終わりのある暑かった日の夕方に、水浴びをする子供たち。暑かったであろう1日を感じられる色使いで描かれた風景からは、温度や日差しも感じられるような気がします。私が田舎で育ったからかもしれませんが、この原風景を呼び起こす描写にしばし足を止め、幼い頃の記憶が目の前の1枚とリンクするような、そんな不思議な感覚を思い起こさせてもらいました。
残念ながら、上記の絵画は撮影不可だったので、代わりに別の1枚を ↓ 。

2023/4/2 上野 国立西洋美術館より